こんにちは、新井一二三です。
今回は2016年7月公開、総監督・脚本が庵野秀明、出演: 長谷川博己、竹野内豊、石原さとみ、大杉漣の「シン・ゴジラ」を採点します。
◇
曇り空と公害と汚職。昭和の主なイメージはこんなところで、だから映画もゴジラもその世相が反映された。だからこそ怪獣エンタメの枠組みを超えてゴジラが長く愛されるゆえんなのだが、だったら今の時代のイメージとは何か。言うまでもなく「ウイルス災害」である。その視点から「シン・ゴジラ」を見てみるとどうなのか。そんな思いで再見してみた次第……。
庵野秀明のひとつの「到達点」。
「シン・ゴジラ」2016年7月公開で総監督は昨日60歳を迎えた庵野秀明。いうまでもなく「エヴァ」に代表される日本のインディペンデントアニメ会社「ガイナックス」の潮流を生み出した日本アニメ業界の巨頭であり、確固たる自分の作品観を持ち続ける「監督らしい監督」である。
庵野はたびたび日本特撮業界のロストテクノロジー化を嘆いており、その中で自称「雇われ監督」としてこの「シン・ゴジラ」が生み出されたわけだが、その彼の野心というか思いみたいなものがなみなみと注がれたこの作品は各界で激賞。あれやこれや第40回日本アカデミー賞やらなんやかんやと受賞しまくり、その中には「日本レコード大賞特別賞」なんてのもあり、もしかしたら怪獣映画が社会現象を巻き起こした最後の作品、と言えるかもしれない。
(シン・ゴジラ音楽集 サウンドトラック鷺巣詩郎 鷺巣詩郎・伊福部昭 )
ゴジラと特撮とリアリティ。
激賞された当時はリアリティがどうのこうのと論じられた傾向が多いように感じるが、僕からしたらリアリティってなんなんだ?という気はする。あくまで「怪獣映画」にリアリティを掛け合わせたエンタメがそこにあるだけで、リアリティがあるから面白いわけではない。というかリアリティを追及したら面白くない。「それっぽさ」を新鮮に見せるのが庵野秀明の真骨頂でもあり、それが「ウルトラセブン」などから見える昭和特撮の本質でもあるような気がする。
今翻って見ると、実は役者の演技に目を見張る。役所広司のように役者として特別な輝きを放つタイプはいないが、それぞれがそれぞれのする役割を完ぺきにこなしている。いやむしろ庵野演出そのものが演技の「それなりっぽさ」を増幅する仕掛けがあるのかもしれない。
作品から醸し出される庵野の熱量、役者の熱量。
全員の役者にあてが書きをしてみせて、そのキャラクター性を増幅させる。長谷川博己、竹野内豊、石原さとみ、大杉漣。チョイ役のマフィア梶田にしてもそう。ようはつまり、「熱心で丁寧な演出」であるということで、その庵野の熱量が役者の真摯な演技を引き出しているという気がしてならない。言葉にすると陳腐だけど、結局それがすべてということは、ありえる。
公害がもたらすおぞましさと先行きへの不安感。それにうわさがカオスを産み昭和という曇り空が作り上げられた。「シン・ゴジラ」が公開されたのは3.11のあとだから、皆このゴジラを自然災害だとみたてて鑑賞した。今見れば、「ウイルス」だと見立てて鑑賞することだろう。作品の最後で人類の完ぺきな勝利は描かれていない。世間に復興のイメージはまだなく、おそらく「新種のウイルスにおびえる」社会はずっと続くことだろう。そう思うと、「シン・ゴジラ」はさらにおぞましさを増す。84点。
◇
ちなみに2020年5月現在では「amazonプライム」で視聴できる模様です。興味のある方はこちらから視聴をぜひどうぞ。無料期間の視聴がおすすめです。



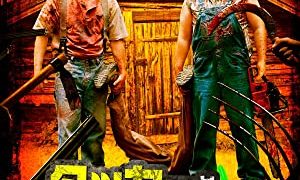







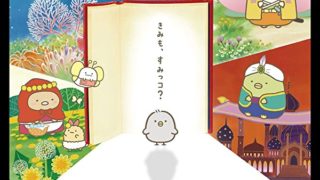

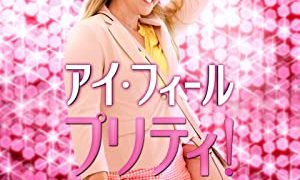






コメント